いまAI業界で最も注目を集めているのが、OpenAI・NVIDIA・Oracleの3社をめぐる「循環取引」疑惑です。
巨額の資金が3社の間をぐるぐると回り、まるでAI版バブルのように市場価値が膨らんでいるという話題。
YouTubeで解説を行った安野貴之氏は、この取引の背景に「国家規模のAIインフラ構想」があると指摘しています。
本記事では、その循環構造の実態から「スターゲート・プロジェクト」、そしてAI産業を支える4つのレイヤーまで、動画内容をもとにわかりやすくまとめました。
出典:【AIバブル?】OpenAIをめぐる循環取引の背景とは? / NVIDIA、OracleのねらいとAI業界のレイヤー構造をゆる解説
OpenAI・NVIDIA・Oracleの循環取引とは?
循環取引とは、特定の企業同士が相互に投資・契約を行うことで、資金が循環し「見かけ上の価値」が高まる仕組みを指します。
AI業界で話題になったのは、2025年に相次いで発表された次の3つの取引です。
- 2025年9月22日:OpenAIとNVIDIAが約15兆円規模の戦略的パートナーシップを締結。
OpenAIはNVIDIA製GPUでAIデータセンターを構築し、NVIDIAはOpenAIに巨額出資。 - その12日前、OpenAIはOracleと約44兆円規模のインフラ構築契約を発表。
データセンターの建設・運用に関する大型案件でした。 - さらに同年5月、OracleはNVIDIAから約6兆円相当のGPUを調達すると公表。
結果として、NVIDIA → OpenAI → Oracle → NVIDIAという形で資金・契約が循環。
安野氏はこれを「AI時代の資本の連鎖」としつつ、3社がそれぞれ異なる目的を持っている点を強調しました。
- OpenAI:人類を超えるAIを実現するための演算能力確保
- NVIDIA:自社GPUの世界的シェア拡大とエコシステムの支配
- Oracle:クラウド市場での出遅れをAIインフラ領域で挽回
3社の思惑が重なった結果、巨額の資金が短期間で動く構造ができあがったのです。
背景にある「スターゲート・プロジェクト」とは?
この循環取引の背後には、米政府主導のAIインフラ計画「スターゲート・プロジェクト」の存在があるといわれています。
2025年1月に発表されたこの構想は、4年間で約75兆円を投じてAI用データセンターを整備する国家級プロジェクト。
主要出資者として、ソフトバンクグループ、OpenAI、Oracle、中東系ファンドMGXが名を連ね、
ソフトバンクの孫正義氏が会長、OpenAIが運営を担う形で進行しています。
この計画では、全米に10GW規模のAIデータセンター群を構築する方針で、
NVIDIAやArm、Microsoftなどが技術パートナーとして参画。
電力は当初、天然ガスによる供給が中心ですが、将来的には原子力や再生エネルギーへの転換も視野に入れています。
AI開発の基盤となる計算能力を確保するため、エネルギーとデータが国家レベルで結びつく時代が始まりつつあるといえるでしょう。
AI業界を理解するカギは「4層構造」
動画内では、AI業界を理解するための「4つのレイヤー構造」が解説されています。
上位層は下位層に依存する仕組みとなっており、これを理解すると業界の力学が見えてきます。
- 半導体レイヤー
AIの計算を担うチップ(GPUなど)を製造する層。NVIDIA、AMD、Broadcomが代表格。 - データセンターレイヤー
大量のGPUを稼働させる物理インフラ。AWS、Azure、Google Cloud、Oracleなど。 - 基盤モデルレイヤー
大規模AIモデルを開発する層。OpenAI、Google、Anthropic、中国勢などが参入。 - アプリケーションレイヤー
ChatGPTのようなサービスを展開し、実際のビジネスや消費者向けアプリを提供。
この構造を俯瞰すると、上層ほど下層の企業に依存し、下層が市場の支配力を持つことがわかります。
とくにNVIDIAが強大な時価総額を維持している理由は、この「最下層=必須の計算インフラ」を独占しているためです。
AIバブルなのか?産業バブルという新しい見方
循環取引が報じられると、「AIバブルだ」との声が上がりました。
互いに投資し合う構造は価値を釣り上げやすく、どこかが資金を止めた瞬間に崩壊する危険もあります。
しかし、安野氏は動画内でジェフ・ベゾス氏の考えを引用し、
「今回のAIブームは金融バブルではなく“産業バブル”に近い」と説明しています。
過去のITバブルやバイオテックバブルと同様に、資金が過熱しても最終的にはインフラや技術が社会に残る。
たとえ一時的に評価が下がっても、AIデータセンターやネットワークなどの物理的資産は、
次世代の技術進化を支える土台になるといいます。
つまり、AIバブルは「崩壊しても恩恵を残すバブル」としての側面を持っているのです。
投資家が押さえるべき3つのポイント
安野氏の解説から導かれる、AI業界に投資・参入する際のチェックポイントは次の3つです。
- 需給の源泉を把握する
AI開発のどの層で実需が発生しているかを確認。資本循環だけで価格が上がっていないか注意。 - 集中リスクを避ける
同一テーマに過度に依存しないポートフォリオを構築。分散とキャッシュ確保が重要。 - インフラの残存価値を見る
仮にバブルが終息しても、残る技術や設備の再利用価値を見極める。長期的な視点を保つ。
まとめ
OpenAI・NVIDIA・Oracleの循環取引は、AI業界全体の構造変化を映し出す象徴的な動きです。
短期的には資金の過熱や評価の偏りを招く可能性がありますが、
同時に、AIインフラや技術が社会全体に広がる契機にもなっています。
AIバブルを恐れるのではなく、その裏にある「産業構造の転換」に注目することが、
これからの時代の正しい投資視点といえるでしょう。

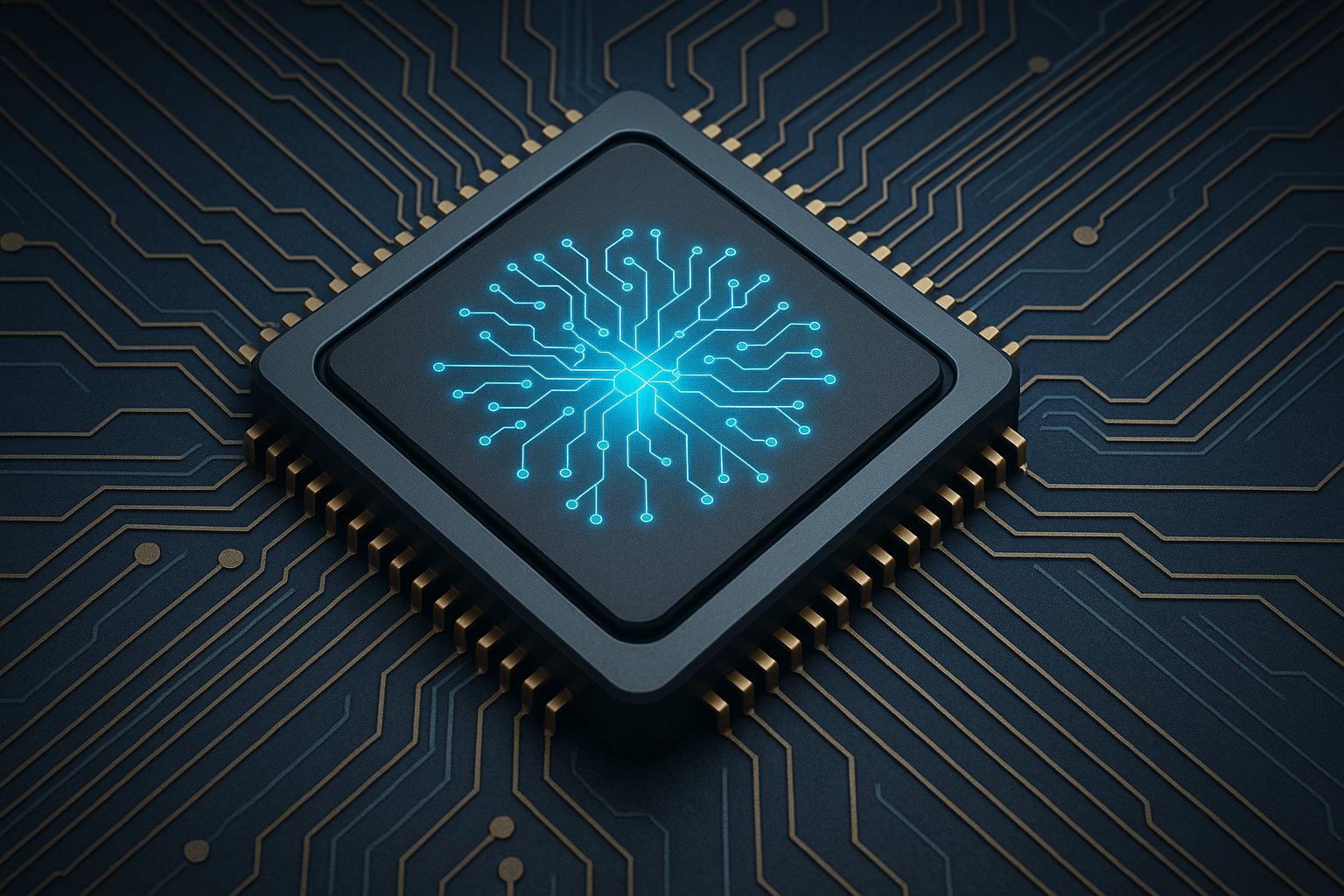

コメント